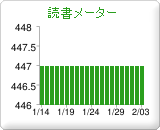2014年も最後の日。今年1年に読んだ本の中から,面白かった本をいくつか振り返ってみる。
社会心理学,行動経済学的なメカニズムを社会変革にどう生かすことができるか,遺伝や生物学,生理学の新しい動向,そしてそれらを社会が受け止め,個人はどう選択するのか,といったテーマがいまの関心事。結果的に,2014年のもののほか,刊行から5年以内の本が中心だった。
ここで挙げているものがすべて翻訳書だった。研究者がまとめたものもあるが,サイエンスライターやジャーナリストがまとめたものも多く,膨大な文献を渉猟し,多くの関係者にインタビューを重ね,それを1つの物語にまとめている。そのあたりがやはり海外のものが厚いのかもしれない。
あと,挙げている本は少ないが,組織やチームの問題についての書籍をいくつか読んだ。組織としてクリエイティブで,創発が起きるために何が大切なのか,というのも興味深いテーマである。
それぞれの本は1冊で完結しているが,関連図書や参考文献の中につながることも多い。そうした偶然や出会いがけっこう楽しい。本を群として,流れとして結びつけていくのは面白いなあと思う。
- ジョナサン・フランクリン『チリ33人―生存と救出,知られざる記録
』共同通信,2011年
絶望の中で人はどう生きるのか。2010年にチリのサンホセ鉱山で起こった落盤事故。33人の鉱山作業員が閉じ込められ,69日後に救出されたこの事故は,多くのメディアによりリアルタイムで報じられ,大きな注目を浴びた。18日目,小さい穴が700mまで貫通。33人が避難所に生存していることがわかる。それまでの17日間はどのような心境だったのか。33人もの集団が,規律をもってきちんと生き延びたことはまさに奇跡的だ。しかし,奇跡の背後には,劣悪な労働環境,メディアの喧騒,政治的駆け引きが透けて見える。
- クレイ・シャーキー『みんな集まれ! ネットワークが世界を動かす
』筑摩書房,2010年
ソーシャルなツールやネットワークが,世界をどう動かすか。ウィキペディアの事例はなかなか興味深い。しかし,ウィキの仕組みを用いたほとんどのサイトやサービスが,人が集まらず失敗をしている,というのも事実だ。ソーシャルで何かを動かすには仕組みが必要なのだ。世界は人が動かしている。ただし,どう動けば(場合の寄っては動かせば)世の中が動くのか,というのは難しい問題だ。
- A. V. バナジー&E. デュフロ『貧乏人の経済学 – もういちど貧困問題を根っこから考える
』みすず書房,2012年
貧困のただ中にいる人には,それに適応した行動習慣が備わっており,それを無視して何か支援をしようと思っても,まったく効果が望めない。熱意だけじゃだめなのだ。置かれた環境での行動様式に沿ったアプローチが必要であり,そのためにはきちんと現場で観察をすることと,結果を実証的な枠組みで分析し,次に生かさなくてはいけない。政策や開発経済においてエビデンスに基づいた議論を行うことは,多くの困難に直面せざるをえない。しかし,そのことを避けて,支援を洗練していくことはできないのだ。
- フランシス・S.コリンズ『遺伝子医療革命―ゲノム科学がわたしたちを変える
』日本放送出版協会,2011年
遺伝子診断,遺伝子医療が,いまどこまで進んでいて,今後どういうことが予想されるのかを,第一線の科学者が解説する珠玉の一冊。遺伝子ですべて予想できるはずもないが(その難しさも描かれている),遺伝子医療により,より健康的に過ごすことが可能になる人たちは間違いなく増える。しかし,単純な明るい未来が待っているわけでもなく,多くの問題をはらむ。なぜなら,遺伝子も社会経済的状況も平等でもないから。賛否を議論する前に,知っておきたいベースとして最適であろう。
- デイビッド・プロッツ『ノーベル賞受賞者の精子バンク―天才の遺伝子は天才を生んだか
』早川書房,2007年
これはかなり面白かった。1980年代に「ノーベル賞受賞者の精子バンク」という触れ込みで始まった「レポジトリー・フォー・ジャーミル・チョイス」。なぜこのバンクはつくられたのか?精子を提供した人は誰だったのか?生まれた子どもは「天才」なのか?母親は「優秀な子ども」に何を託したのか,そして育ての父親の意味とは?生まれた子どもは何を思い,自分の「生まれ」にどう対峙するのか? この精子バンクは閉鎖されたが,その後より洗練された形で精子バンクが活況に湧いている。そこで生じている問題の原点がここにある。
- デボラ・ブラム『愛を科学で測った男―異端の心理学者ハリー・ハーロウとサル実験の真実
』白揚社 ,2014年
ハリー・ハーロウ。有名な,「愛情」にまつわるサルの実験を行った心理学者の物語である。当時は行動主義全盛で,「愛情をもって子供を育ててはいけない」といわれていたらしい。愛情を持つことが大切だ,と私たちが常識として思っていることは常識ではなかったのだ。精緻な,そしてインパクトのある研究を展開していく。しかし,愛情を強調することで,女性運動家から強く非難され,そして研究手法の倫理的な問題も指摘されてしまう。研究はもちろんのこと,家族や同僚たち,当時の社会状況など,重層的に話が展開され,非常に面白い。
- シッダールタ・ムカジー『病の「皇帝」がんに挑む 人類4000年の苦闘(上)
病の「皇帝」がんに挑む 人類4000年の苦闘(上)
』早川書房,2013年
がんに人類は以下に挑んできたか,そして挑んでいるか。がんに対する様々な見方,そして治療について,歴史的に書かれている。原因も治療法も,「がん」だからと一緒くたにできない。遺伝学や生理学的なアプローチがいまは最盛期だが,実際の治療は生身の人間で行われており,その「生々しさ」も感じられる。上下巻とボリュームは大きいが,最後まで勢いは衰えず,おもしろく読んだ。
- アリス・ウェクスラー『ウェクスラー家の選択―遺伝子診断と向き合った家族
』新潮社,2003年
遺伝的要因の強いハンチントン舞踏病。その遺伝的な影響に直面したウェクスラー一家(ちなみに,父親と妹が精神分析であり,そうした世界観が垣間見える)。団体をつくり,神経科学の基礎研究への支援を行っていく。さまざまな困難にあいつつも,遺伝子診断を実現するために突き進んでいく。そして,いざ遺伝子診断が現実のものとなったとき,遺伝子診断を受けるのか,受けないのか,という決断に迫られ,迷いが生じる。かりに発症する可能性があるとわかっても,それがいつ起きるのかは予想できない。そうであれば遺伝子診断の意味は何だろう?
- モイセズ・ベラスケス=マノフ『寄生虫なき病
』文藝春秋,2014年
なぜアレルギーが増えたのか? さまざまな研究を手掛かりに,腸内細菌叢や寄生虫にその原因を見出す。ついには自身の体に寄生虫を取り入れ,実験を行う。とはいえ,そう簡単にはうまくいかない。体調も崩す。また,そのことに取りつかれた人物もいささか滑稽である。しかし,人間の体は微妙なバランスの上に成り立っていることは疑いがなく,現代の衛生環境がある側面で悪影響を及ぼしうるのはありうることだろう。これまで知らなかった世界を拓く,非常に面白い本だった。
- マイケル・モス『フードトラップ 食品に仕掛けられた至福の罠
』日経BP,2014年
糖分,脂肪,塩分。アメリカ食品業界はこれらを武器に,国民の食生活と健康に強く働き掛ける。食べるのをやめられないようにするにはどうしたらよいか,食べたくなるようなイメージをどうすれば作り出せるのか。巨大な食品企業の商業主義に対して,研究者や一企業家の信念はあえなくくじかれていく。そうした食品企業の幹部たちは,自社の商品を食べることはなく,健康的な食生活に励むという逆説。人の身体的欲求の前に,理性は無力であること,そしてマーケティングの負の側面を痛感させられる。
- トム・ケリー&ジョナサン・リットマン『発想する会社! ― 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法
』早川書房,2002年
IDEOについて知らなかったが,最初のスーパーマーケットのカートをつくるプロセスから圧倒される。そして,それぞれが美しい(機能的にも,見た目も)。電子書籍やウェアラブルについてもしっかりと書かれていて,これが10年以上前の本だというのにびっくりする。ただ,イノベーションを起こすこととそれが市場に受け入れられることとは単純には結び付かないようで,そこにはタイミングやマーケティングの要素が強く影響するのだと思う。
来年もいい本に出合えますように! そしてもっとちゃんとブログを更新できますように。